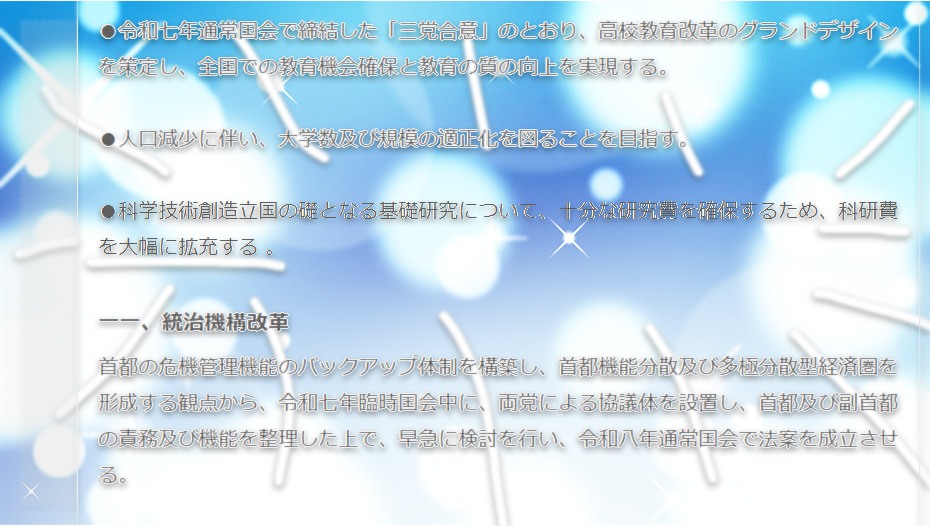| ホーム | What's New! | 錦魚屋敷 | オルフェウス ゴーシュ | Linux | モバ | Links | 訪問者の部屋 |
What's New!
.Lastupdate: Wed Dec 10 08:41:33 2025.
|
12 月 10 日: 手を動かし続ける
ところで,定年後のシミュレーションをする機会が多いのですが, 老害化しない唯一最大のことは,「手を動かし続ける」ことだと思いました. 我々,職人なので.
転職したよ,するよって50代60代の皆さんの話を伺うことが,めちゃめちゃ多くて.
いえ,僕ら経験値もついてきて,大所高所からモノを語れるようになりますやん.で,「教授」とか「部長・役員」とかだったら,若い人,下の人を口でコントロールして成果を出させるというやり方が普通だし,問題ない.けど,辞めた途端,それは意味がなくなる.その大所高所にしたって,たとえば僕らの分野だとシミュレーションと AI はどんどん融合してるわけだが,Python も使えない人が「助言」してくれたって,そんな古い技術しか体感してない人の意見は要らんわけです.だから,手を動かし続けるか黙るか,どちらかじゃないと,老害になる.僕がオリジナルのソフトを書き続けてるのは,それが理由です.手を動かしてる老人でムカつく人に会ったことがない.80 歳になっても論文を書かれるのか,っと呆れることはあっても.で,そういう人にこそ,次世代へのメッセージを伝えていただきたいと思うわけで.
10 月 26 日: 高校生の好奇心に対応するためのトレーニング,キャリアプラン
すべて偶然なのですが.
今日は高校生の研究テーマ提案を聞いて,一件一件,助言をする会でした.純粋なデータ科学や計算科学以外に,農業,音楽,交通,エネルギー問題など大変幅広い提案をしてきます.いちいち,真面目に対応します.
自分で言うのも何だが,かなり向いてると思う.駒場のリベラルアーツの文化※1,自動車研究所の理工系なんでもありの研究文化※2,そして神戸に来てからのシミュレーション学の自在性※3,全部が高校生と向き合う原動力になっていると思いました.
本当,中には既に修論かよって感じの下調べをしてる子がいます.バックにブレイン(親とか)がいるんじゃないかと疑って質問しても,ちゃんと答える.論文だけでなく,パブリックなデータにもちゃんとアクセスして読み取っている.ほぉっと思います.
誰かの何かの参考になるか知らんけど.
※1:本郷では,その学問の king になろうとするけど,駒場の人々は本郷で王朝を作れなかった分野の人々がやってるので,境界領域・融合的な分野の人々が集まってしまう.カオスなんて典型だが,宇宙論だけど計算機が好きすぎとか,生物物理化学とか→全部じゃねえか.文系だと村上陽一郎とか東浩紀とか舛添とか.最近,駒場の後輩が同僚教授として着任されて,そういう話をしていました.
※2:自動車工学の一番面白いところは,目的のためには手段を択ばないので,学問とは逆問題の方向性を持っていること.構造材料として金属(鉄)と軽金属(アルミ・チタン)が常に戦ってる(こいつら別の学会だって知ってました?).そこにセラミクスが参戦する.構造材料として負けたら機能材料を突然言い始める.「透明マント」を作りたい,って研究室は,材料が何であれ,機構が何であれ構わない.普通は,エンジニアというのは,特定の材料(ポリマーが好きとか,二価の陽イオンが好きとか)とか機構(ピストンが好きとか)に拘るものです.そこが自由すぎて怖い面もある.
※3:シミュレーション学は自由です.雲の研究のために構築したシミュレーション方法で,自動車の塗装の研究をしたり,エンジンの燃焼の研究ができる.霧吹きの要領なので.とか.プラズマの流れのシミュレーション手法によって,木星の大赤斑の安定性の議論ができる.あれ,少なくとも400年安定なのです.僕のグリースのシミュレータを使って血液中のタンパク質のシミュレーションができるのも似たような話.コンピュータだと,学術分野をひょいと超えられる.
10 月 21 日: ついに「選択と集中」から道を改めるの,か!?
東スポっぽい見出しになってしまいました(懐かしい).
> 科学技術創造立国の礎となる基礎研究について、十分な研究費を確保するため、科研費を大幅に拡充する 。
これ, 自民党と日本維新の会の連立政権樹立合意書です.
研究費は上がらないのに物価があがって困る,という状態を解消していただくのはもちろんなのですが,根本的な問題は「選択と集中」.「勝ち馬に投資したら良いじゃないか」という安直な発想で,ここ20年ほどの研究費配分は行われてきました.財務省の神田さんはじめ,官僚・政治家はじめ,主だった研究者の皆さんも賛成していたフシがある.私は長らく民間人だからどうでも良かったけど(笑).
お蔭でボロボロだ.勝ち馬っぽくない分野である,高分子電解質溶液論も,トライボロジーも,東大からなくなった.学術体系を作って,最後に本を書く大先生は激減して,Nature だ Science だを何本ホールドしているかだけが自慢の研究者の大学になった.リスペクトの軸がずれてしまった.
スパコンは,バイオと同様に税金が大量投入されてるから救われてる部分があるが,テーマは「勝ち馬」っぽいテーマに厳選されてしまっている.高分子電解質溶液論ができないから,電池の研究をしているフリをして,私も「選択と集中」の波に乗った部分はある.京コンピュータを作るプロジェクトでも,無理やり潤滑のテーマを載せた.
そういう研究者は沢山いる.本郷で高分子電解質論をやっていたグループは,国土強靭化と同じ強靭化というワードを得て,膨大な資金を投下された.費用対効果はわからない.納税者へのキラキラした説明をしながら,そういう人でも正気を保ってる部分でまともな論文を出しているので,それがアウトプットの実体と考えれば悪い話ではない.しかし,表の説明にあった,自動車のボディのポリマー化は,全然未達成.
本来は,同じ研究費を,国プロではなく,それぞれが科研費としてもらうのが筋だったのではないか.スパコンは,5年,10年といったプロジェクト区切りでゼロかいちかで配分するのではなく,基礎的な資金として長く担保すべきだったんじゃないか.一度クビにした技術者は戻ってこないので ※注1.皆さん,そろそろ正気になったらどうでしょうかね.
この 2 党合意,「科研費」という言葉を,「SIP みたいな,内閣府ではなく科研費」「JST の CREST, 云々ではなく科研費」という意味で使っているのだったら良いのですが,ボヤっと科学技術の研究費の代名詞として使ってる可能性はあります.
でも本当,科研費とかの審査員をやってると,「こりゃ落とすべきだな」という提案は 2-3 割くらいで,「まあ,やってみたら良いんじゃない」というテーマが多数です.そりゃそうだ.研究者として生き残ってる人々が書いてる提案なので ※注2,変なもんはそんなにはないよ.生き残ってるお前ら,超リスペクトですよ.
だけど現実は逆で,2-3割を通して7割落としているのです.本当,バカバカしいったらありゃしない.
たとえば,採択率を今の倍ちょっとの6割にするだけで,基礎研究の世界はだいぶ変わりますよ.
人間は使い捨てではないのだ.企業研究者の人なら知っている.採用するために,どれだけのコストをかけたか.こいつを一生働かせるために,どんだけ教育してアイディアを出させて資本を投下したか.
でも,大学の場合は,義理も人情も基本ないし,大学運営(教授会)と教育(授業と入試)をやってたら怒られない.どうなるかというと,学生を研究室で育てたり,研究費をとって論文を書くことは「趣味」みたいに扱われる.
結果,人材やアイディアの使い捨ては当たり前,ということになる.見ず知らずの人の研究費の提案を落とすなんて当たり前,という感覚が,それこそ当たり前になる.それ,アタオカですよって思いますよ.上流から金がキューっと絞られたから,麻痺しているのです.ああ,研究開発費1兆円の会社で良かった. ※注3
アカデミアは,企業社会より腐ってます.なのですが,私は54年前に無給で研究室で研究をしていた旧帝大の37歳「副手」から生まれた,より腐ってた頃のアカデミアで誕生した,腐海の王子なので ( 2021 年 1 月 28 日 実は腐海生まれ), 何も言いますまい(って言いまくってるけど).
※注1 こういう部分的な意見は,僕らも国に聞かれて答えてるんですけどね.それなりに伝わってはいる.
JST CRDS 戦略プロポーザル:計算物質科学の新展開 ~デジタルツインによる材料創製基盤の革新~ 私もコメンテーターとして参加しました.
※注2 「研究者として生き残る」のリアリティを一番良く知ってるのは自分です.一度,研究者ですらなくなったので.研究能力を全否定されたわけだ.だけど,この10年で科研費でいうと代表5件,分担8件やってます.どう考えても研究のプロだ.失礼ではないかね,諸君,っと今なら言いたい.当時は「ひょえ~,やっぱダメか」と思ってたのですが.
※注3 自動車全体の開発まで含めて1兆円なので,単純比較してはいけないが,科研費って,たった総額 2,300 億円なのですよ.でも他に「選択と集中」の予算が,各省庁いろいろあって,それを軸に「ビッグ」な先生たちが戦ってるのが,今のアカデミアです.ちょっと笑える.彼らは実際ビッグではあるんだけど,5万回引用されてる先生などと付き合った結論からいうと,別に僕より2倍もビッグというわけではない ( 2021 年 2 月 25 日: 「2 倍凄い人」はいない ).そういうもんです.
10 月 5 日: 地理かぁ・堀越先生の想い出
子供は高 1 なのですが,理系を選択すると社会科は地理を選ぶことを 勧められるようです.日本史は小学校から何度も習った上での 大学受験なのでマニアックになり,世界史は広すぎるので,ということで, 地理の点が取りやすいそうです.なるほど.
なのですが,理系の人ほど,歴史をしっかり勉強するのは 大事なのではないかと思います.
僕は講義で,「分子の発見」の歴史を必ず入れています. 1905 年,奇跡の年にアインシュタインは 3 本の論文を 書くのだが,そのうちの 1 つがブラウン運動の理論だった. その論文から得られる教えは,コロイド粒子の動きを測定することによって, その動き=熱揺動の原因となっている小さい水分子の存在を証明できる, ということです. 早速,1908 年にペランは実験的に水分子の存在を証明しました. 分子論というのは,今では当たり前ですが,このように 20 世紀に入らないと証明されなかったのですね. このため,分子論に基づく統計力学を構築したボルツマンは, 対抗する重鎮だったマッハに,分子の実在を証明しろと迫られ, 1906 年に自殺します.あと 2 年生きてればなあ,という話です. 米沢富美子,ブラウン運動,共立出版 (1986).
このように自然科学も人類の営みです.
それで思い出したのが,学部時代の教授だった堀越弘毅先生です. 堀越先生は,極限微生物学の大家だったわけですが, 全然授業をやってくれなかった.ずっと助手の先生が来てました (今では考えられない 笑). で,最後の講義だけご本人が現れて,次のようなお話をされたのです.
(1) 自分の発見を盗まれるな.(2) 理学・工学の両方からみて良い研究をしろ. どういうことかというと, 自分は農学部で博士号を取って国研に入った(農研だと思ってたら理研だった). 当時,微生物は中性か弱酸性の条件で生きていると信じられており, それがパスツール以来の常識だった. しかし,自分はアルカリ性で生きられる細菌を発見した.
そのときどうしたかというと,この新発見を上司から隠したそうです. なぜなら,自分も含めて科学者なんて凡人だから, いくつも凄い発見をすることは無理だ.せいぜい人生で一つだ. だから,それを大事にしなさい,と. で,2 年間追試をしまくった.
この発見には,理学的な側面と工学的な側面がある. 理学的には,アルカリ性で生きられる細菌の存在自体が大発見であるが, その考えを広げていくと,高温で生きられる生物,低酸素や無酸素で 生きられる生物など,極限環境下で生きられる生物についての 学問体系の入り口となる,ということです. 工学的には,アルカリ性で生きられるということは,酵素活性の ピークがアルカリ側にあるということです(生物学を勉強しないとわからんかも). ということは,アルカリ溶液である石けん水の中でタンパク質を 分解できたりするわけだ.これが,洗濯石けんにおける酵素パワーの発見であり, 洗剤の箱のサイズが 2-3 割くらいに小さくなったでしょう(年配しか知らないだろう), あれです.
同時に,自分より先人の研究者の誰も全く気づいていない,ということは 有り得ない.ので,先行研究を調べまくったと. そして,それを体系的に記述して,その上で,その歴史の最も先端に 自分自身の研究がある,ということを位置づけたと.
歴史,大事でしょう. 歴史を知るということは,先人をリスペクトするということであり, 自分を世界に位置づけるということであり, 単なる一技術者から文化人になる入り口なのだと思います. 科学者は文化的であらねばならない.文化的じゃなくても 研究自体は出来るんですけどね. ということで,気軽に読める科学の歴史のお勧めは,たとえば 北原文雄 コロイド化学史,サイエンティスト社 (2017).
それにしても,この堀越先生の講義は,学生時代を通して一番印象に残った講義でした. もちろん,直接の恩師は非線形物理や統計力学を教えていただいた槌屋先生, 高分子物理や電解質溶液論を教えていただいた菊地先生なのですが, 一番ウケた,というか人生の指針になった,というか.
10 月 1 日: 研究室 10 年
おかげさまで,昨日で大学に移って丸 10 年です.「研究ベーシスト」の芸風を確立できたのは,間違いなく皆様のお蔭です.多謝であります.
いやはや,2001 年に博士号を取ったときは,どんだけショボいポストでも良いからアカポスに就きたかった.というのは,現代詩人の多くの表の稼業は大学の先生だったので.この分野のちょっと先輩に現代詩人の田中庸介さん(表の稼業は東大医学部講師)がおられます.
しかし,夢だった「湘南女子大学の自然科学のセンセ(田中さんほど賢くないので,こんな感じかなと妄想したポスト.若者の未来について責任を負わずに自然の神秘を語れば良い,素晴らしいポスト)」職はおろか,北は旭川高専から南は松江高専まで,現実的なすべての夢に破れ,ひょんなことからトライボロジー業界でお世話になることになりました.
これがハマって,14 年間,前職でお世話になりました.最後の数年間は,自分の研究グループを先端研究センターに作らせていただいて,やりたいテーマを,豊富な資金とスタッフでやらせていただいてたので,何も不満はありませんでした.
そして,10 年前にひょんなことからアカデミアに戻って参りまして,余計に産業のために尽力することとなりました.「研究ベーシスト」として尽力した成果は,まあ論文もありますが,何よりも,トライボロジー業界で活躍している若者たちだと思っています ( 修士院生の就職先一覧). 同じ業界の先輩方を見て,狙った通り,軸受,潤滑油,機械,電機,自動車,CAE,などの人材を育てる場所を作れました.あと 10 年ほどですが,頑張って研究開発者を育てますので,宜しくお願いいたします.
カウントしますと...
博士 15 名(うち当研究室の修士4,文科省国費留学生1)
修士 43 名(うち博士に進学4)
高校生 4 名
特任教員等 14 名
研修員 1 名
交換留学生 1 名
原著論文 41
レビューなど 39
招待講演 106
学会発表 469
科研費 代表 5
科研費 分担 8
NEDO とか元素戦略とか地域なんとかとか無数
企業との共同研究 35 社
9 月 26 日: 自分には「趣味」がない,ことに気づいた話
「趣味がない」ってことですが.ちょっと心の整理がしたくて.
何の整理かというと,ある企業さん(初対面)から,「ワシヅさんの技術を使いたいけど,金がないから,ワシヅの友達のT大教授の研究室の学生さんに無料で教えろ.んで,自分たちがしたい系の解析を実施する」という話になったそうで.
何を言ってるんだ?っと,T大の先生からメールいただいて.怒ったので,ちょっと心の整理がしたくて.
ちょっと前のことですが,科研費の事務を主にやっていただいてる本学職員の女性と,帰宅するときに一緒になって,「自分には趣味がない」って話をしてました.
いえ,我々の担当している科研費「チェロの力学」が面白いって仰られるので,あー,あれは趣味みたいなものなんですが,実は趣味じゃないのですよ,っと.
今後の予定としては,お世話になってる小説家の先生のテキストデータのマイニングをやる予定で,そんな感じで文系,芸術系の研究もどんどん進めて行きますよ,っと.
逆にいうと,若い頃から,現代詩を書いたり演奏・作曲したりしてますが,あれは全部,「趣味」じゃないのですよ,っと.ガチなんです,って話をしてました.僕は「知の巨人」(笑)になる予定なんですよ.理系に限定しないで欲しい.
チェロの演奏とか,小説なんてものは,既に現代文明の一部ですよね.間違いなく.で,それを研究する,ということは,何というかエスタブリッシュされた話なのです.ですので,端的にいうと「研究費がもらえても何の不思議もない対象である」ということです.
だから,研究するなら金をくれ,っと思います.中途半端な,ペチョペチョした,アマチュアイズムが大嫌いなのです.
アマチュアイズム自体を嫌っているのではなくて,「もし金にならない研究をするなら,まだ学問になっていないような,大事なこと」をすべきだと思うのです.
ワシヅのご先祖は,そういう研究をしていた. 2023 年 8 月 12 日: ご先祖と語らう
別の観点から,「手弁当で研究会をやっているのですよ」とかいう言い方があります, 講師に謝礼を出せない,といったことがありますよね.が,それは, 恥ずかしそうにするべきことです. プロになれる筈なのになってない,ってプロモーション能力も含めて,無能ということですので. そういう状態が多々あるのは知ってますが,威張ることじゃなくて,恥ずかしそうにして欲しい.
チェロの演奏をする,という例に戻って引っ張ると,アマオケの正式な団員にならないのも,この考え方の延長線上です.
世の中には,金を払って演奏させてもらう人と,金を貰って演奏する人がいます.大半の人は,前者になるわけですが,僕は,厳しく自分を律してます.
金を貰うか,ゼロ円で参加するんだったら,チェロを人前で弾くことにしています.アマトラ(エキストラで管弦楽団でチェロを弾く)というのは一回 5,000 円貰うのが相場なのですが,財政が苦しかったらゼロ円で弾きます.でも,団費は払いません,というのが僕の立場です.
何故かというと,そうしないと,際限なく週末が潰れていく.もっとクリエイティブな作業をしなきゃいけないのに,時間が削がれていく.それが嫌なのです.そこでも,アマチュアイズムを否定してます.
なので,結果的に「趣味がない」ということになります.
たとえば,「旅行」も趣味になり得ると思うのですが,自分の楽しみのための旅行は一切しません.海外出張めちゃめちゃ行ってますけど.
家族旅行はしますが,それは,家族のための楽しみです.友人と旅行もしますが,それは,友人から何かを得られるかもしれない,という,欲深い理由に基づきます... というのは半分嘘で,自分が上記のようにストイックだからといって,他人,しかも家族や友人になってくれるような大切な人たちを巻き込んではいけないと思う次第.
ということで,めちゃめちゃセコく生きているわけです.
逆に,なんでも実は趣味なんじゃないか,と言われるかもしれません. でも僕の場合は,「趣味」ってもんを確立する前から,すべてがガチだったんだと思います.趣味からガチへの時間軸が逆というか.
たとえば,音楽については,アメリカのピアノの先生は上手になったらボストンの小澤征爾のところに連れていってやると仰ってました.もっと上手な兄に向っての言葉だったとは思いますが,僕も割とマジで信じていた.これは,職業ですよね?
水泳もそうなんですが,仕事になりそこねたものが趣味みたいになってる,みたいな. 水泳も,浪人してるときスイミングスクールのインストラクターに誘われました. 金を稼げないので,現時点では趣味,みたいな.自然科学も,出版社に入社した時点でダメになりそうだったところ,ぎりぎり職業になってるわけです.
やってること,全部わりとガチってことで.
元の話に戻ると, 失礼な企業さんは「無料で教えろ」っと言ってるわけです.これって,アマチュアイズムです.金を払わずに技術を教えろ,ってことですので.
で,彼らに僕が教える理由があるとしたら,「僕もアマチュアの科学者なので,暇なので教えてあげます」ってことになります.でも,悪いけど,他の企業さんは何百万円も払って,共同研究してくれてるわけです.なんで,この会社さんだけに,タダで教える義理があるのでしょうか.
僕もまあ,ながらく企業研究者だったので,企業側の立場を知ってます.それを思い出すと,余計,失礼.
で,趣味だったら,教えますけど.悪いけど,僕にはそもそも「趣味」って概念がないのです.チェロを弾くのですら,基本的には金を貰うよ(アマトラとして無料で弾いてることもある).という,話ということで.
9 月 18 日: 日本の科学リテラシーと万博
とくに追加の意見はありません. 河田 雅圭 「動的平衡生命観」に生物学的根拠はあるのか ? 問われる日本の科学リテラシー
日本の科学リテラシーの問題は深刻です.シュレーディンガーやプリゴジン,ジャック・モノーが普通に読まれる国と,今西錦司や福岡某ですので... 四半世紀前に出版社に入ったときに,いろいろ頑張ろうかと思いましたが,諦めました.そして,今回の万博(笑)
定年までオリジナルペーパーを書いてる時点で,こういう人々には僕らは圧勝だと思っています.
万博は,何か関われたら良かったのですが,2005 年当時も長久手勤務だったのに半日行っただけで, 今回は行かずに終了してしまいそう.面白そうな外国館はあるように思うのですが, このメイン? のコンセプトは全く同意できないものだらけでした.
8 月 19 日: 在野の研究者
またまた岡部さんからの紹介.面白いなあ. なぜいま「在野研究者」なのか『在野研究ビギナーズ』編著者・荒木優太氏インタビュー
でも,この人には,是非,有島武郎で博士論文を書いていただいて,せめて博士(文学)になってもらって,で,大学とは言わないが,ちょっとは何らかの研究機関で働いて欲しい.文学って,多分エスタブリッシュされた学問なので (学問がエスタブリッシュされていない場合は鷲津の祖先のように ( 2023 年 8 月 12 日: ご先祖と語らう) 私塾を開くしかない).
何故かというと,この人は教育というものが授業だと思ってるフシがあって,それは違うということ.授業の数が教育者としての偉さを決めてるんだとすると,僕の今のポジションは前期で90分を12回しかやってないので(修士9,学部2,博士1),1コマ分にもならない.そこがメインじゃない.今時の科研費の制度だと,非常勤を雇って,このストレスから金で逃げることすら可能だ,ってことを,ひょっとして知らないのでは.
もっと根本的なことを,良く考えるのです.それは,やっぱ「学問には権威が必要」ということ.現時点での,科学的な見地からいって,これこれについてはこういう風に考えるのがスタンダードです,というスタンダードを示す作業が,学会活動であったり大学での研究教育です.
それは,いつも恥ずかしさと裏表です.ドイツ最高の科学者のマッハを,僕は授業で毎年軽くディスっています.ボルツマンを死なせたので.マッハ先生は,まさか100年後の東洋の島国の大学の授業で自分がディスられてるなんて,想像してないでしょう.でも,それを想像するのが,学問をする行為の一部だと思うのです.正しく生きるのは厳しい.
で,学問に権威がなくなっちゃうと,「水の分子のクラスターがモーツアルトを聞いてプルプルになった」的な疑似科学を否定できなくなっちゃう.そもそも,「分子」ってもの自体が,ほんの一段落前に書いた科学史(マッハは反分子論者,ボルツマンは分子論者)の結果として認められたわけで.
で,「在野」という意味では,自分も民間企業でずっと在野だったのですが,一方で論文を書いて学会活動はしてきました.荒木さんが論文を書いてるかは知りませんが, Researchmap を見ると2022年の「有島武郎の森本厚吉批判を再構成する 」有島武郎研究会第72回全国大会が最新の有島武郎研究の成果なのだとすると,もうちょっとコンセントレートして自分の専門を頑張ったら,っと思う.
研究者の価値は,どれだけ真面目な仕事をしたか,だけでして,在野だろうが大学だろうが関係ない.転職早々,10年間論文がゼロだった先輩教授がいて攻撃してきたときに,あの人は研究者じゃないから,と相手にしませんでした.それくらいドライで厳しくて良い.
氏がインタビューで仰ってる通り,大学の先生は,こういう下世話なことを述べません.私は,彼の上をいく「在野」だと思っているので,平気で恥知らずにも述べる,という次第.
8 月 13 日: 戦略的に真面目に生きる
「サイゾー」って雑誌,はじめて読みましたが,この記事がめちゃめちゃ面白かった. Nintendo Switch2 世界が熱狂する理由と任天堂“撤退の決断力”
息子はもう任天堂離れをしてるので買う気配がないですが,Switch2 の記事.転売を防ぐために,徹底して顧客管理をするところ,直接任天堂のサイトで登録して実際にゲームをやってる人にしか売らない.情報管理を徹底していて,映画化の情報をリークするなど「不義理」をした企業とはコラボを中止する.製品についても,コラボレータには部分的にしか情報を開示せず,さらに与える情報に差異をつけることによって,誰がリークしたかを特定しやすくする.マスコミに頼らず,自分たちのメディアを作って情報発信する.
間抜けな日本企業としては珍しいくらい戦略的.で,何に似てるか,といったら T 社ですね(爆).一つ一つの戦略の理由が明確だから良いのだと思います.何かというと,「顧客=ユーザーと直接向き合う」ために,様々な仕掛けを用意するということ.マスコミが電気自動車の時代だとギャーギャー言うからといって,お客さんに電気自動車を売っちゃダメですよ.そのために自社メディアを作るくらいじゃないと.予想以上に思想が似ててビビった.そして,それが今のところうまく行ってる.
こういう行動様式って,個人ベースでさえ学ぶことができると思います.
「不義理なコラボレータとは,勇気を持って切る」とか.最終的には誰のためにこの研究テーマを実施してるのか,とか.
「戦略的に真面目に生きる」というのって,なかなか大変です.何故なら,ズルとか「和を乱す」ことと紙一重なので,日本人はあまりそっちに行かないのだと思うのです. でも,日本ぽい,んだけど(不義理を許さない部分とか),戦略がなく日本っぽくやってしまうと,単に「生真面目な日本人」になっちゃうと思います.で,ずるい奴に良いようにやられる.ビジョンがない奴とコラボすると本来の目的を達成できない.そもそもそれじゃビジネス(研究室の経営とか運営?)として負ける,けど,直感的ですが,戦略を持つことを拒否る真面目な日本人って結構多い気がします.学術的に賢くてレベルの高い人ほど.
「出し抜くのが目的なズル,じゃなくて戦略」「我欲・欲望じゃなくて戦略」っと,自分の道徳心に言い聞かせるのが良いと思います.
8 月 6 日: イギリス兵の具体例
2025 年 3 月 2 日: イギリス兵のように生きてきた について,具体例を一つ思いつきました.
この,T 社系列なら見たことのある空気感の資料 は,KYT とかの安全活動についての厚労省のサイトにある報告書なのですが,メーカー勤務だったので僕もこの手の知識は,まあまああります.で,理論の人とか,「俺は先端研究者で,KYT なんてやってる暇があったら論文を書きたい」みたいな人も,中にはいます.でも,僕は若い頃から,それは直観的に違うと思ってました.他には,交通安全についても凄く時間とコストをかけてやるんですが,それも似てます.
なのですが,今朝,気の毒なことに妻が階段でコケて青あざができました.メーカー勤務だったら,階段を昇降するときは,そのことだけを考えるというのは常識だと思うのですが,メーカー経験がないと KYT やってないし,知らんがなという感じです.
社会に,KYT をめちゃめちゃ知ってる人と,まったく知らない人とがいたら,家庭生活にもこういうのは応用できるので,ビジネスになります.実際になるかどうか知らんけど,少なくとも,あらゆるこういう経験を,ビジネスにならないか,自分の知的生産のヒントにならないか,考え続けながら生きるのが,「イギリス兵のように生きる」ということです.僕の職場の先輩(もう私大に移った)の中野先輩なら,これくらいの思いつきで新書にされてると思う.
7 月 27 日: スイスに 25 年ぶりに来て思った
食べ物代は極力抑えるしかないですが. パン屋さんで,アップルパイみたいなの 3.8 CHF, ピザが 4.9 CHF.1600円!しました. 380 円と 490 円だと思うと,まあ納得できるんですが. めちゃめちゃ B 級の食堂でシャウエルマとかプレート中華とかフォーとか, 旅人に優しいはずのものを食べても 15 CHF とかするので,もう何も外食できません(笑).
「アルプス日誌」(2000年6月) というのを昔,書きましたが, 25 年前は,山のリゾートでフォンデューとか食ってたんですが, 今回は何か食うだろうか... このまま帰宅便でも良いですが. で,25 年前は 1 フラン 70 円! こんな日本に誰がした(まあ,自動車産業がもっともっともっともっと頑張れば良かったのですかね 笑.自民党が悪いんですかね.金融に詳しい人,教えてくださいよ).
こうやって何事もメモをしていくと,いろんな記憶が連結されていきます(まあ,他人にとってはどうでもいいけど).今はFBにメモっているので,甚だ不安. 上の「アルプス日誌」,読んでいたら,チューリッヒ中央駅前が95年まで治安が悪かったとか,はじめて知ったかのような文章であった(笑).で,このときも 4.9 フランでピザを食ってた!(爆).25年,進歩なし...
このアルプス日誌に書いた Hribar さん,カリフォルニアの大学でポスドクやってたと思うのですが, 今みたら,故郷のスロベニアの リュブリアナ大学の教授 になってた.さすが.あれからも,正しく生きてきたのだろうな...
高分子電解質溶液論をずっとやっていたら,「学生時代からの友人が欧米の有名大学の教授になる」ということになっていた.今は,トライボロジーの欧米の有名大学教授に友人はまあまあいるけど,自分より若い人たちばっかりだもんな.学生時代の記憶を共有していない.
とくに理学系の博士の人たちが「分野を変えたくない」というのは,こういうことで,やっぱり分野を変えると,端的にいうと世界レベルから落ちちゃう,ということ.トライボ分子シミュレーションというのは,この分野はもともとはなかったから,まあ別の意味で僕は生き残っているけど,本来の意味では生き残っていないということ.
こういう本質的な,若手の交流を今は立場的にサポートしているけど,自分の学生には,大人になって分野を変えるな,っと,この観点から伝えるべきだろうなあ.日頃は,柔軟に生きなきゃ,とも言ってるけど,柔軟に生きたら負け,ではあるのです.
あと,東大どころか日本から高分子電解質溶液論は分野ごと,ほぼ消えましたが,トライボロジーも東大に3研究室あったのに消えました.最後の先生はせいせいされてたから,ご本人的には良かったとは思うのですが.でもやっぱ,トップの大学から学問分野が消えていくのは,大丈夫なのですかね.学術交流という意味で.リュブリヤナ大学には,高分子電解質溶液論もトライボロジー(こっちの教授は癖強ですが)も残ってまして,という意味で,学問的多様性は人口 200 万の小国の方が高いという.
日本がやっちまった「選択と集中」の結果です.これが,1 スイスフランが 70 円から 186 円に高騰したことと無縁ですかね.
7 月 18 日: 東工大生がモテないメカニズム
突然ですが,東工大生がモテない,絶望的にモテないという事実があって.
姫路工大も,国公立の工大だから似たようなものだろう,っと思っていたら,意外にも,うちの学生諸君はカノジョがいる率が高い.しかも,ヒメタン(環境人間学部⇒もともと短大だったので女子が多い)の学内だけでなく,近所の私大とかの子と普通に付き合っている.羨ましい青春.
で,この謎は,岐阜大工学部出身の友人が,「俺たちもモテてたよ」って話をしたことで氷解した.
姫路工大も岐阜大も,地元ではトップだし,普通に知名度がある.ので,普通にモテる.でも,東工大は「激戦区」の東京にあるがゆえに,ダメなのだ.周囲の早稲田や慶応どころか,明治とか青学とかアルプス連峰のように有名大学が並んでいるので,ダメだったのだ.
戦ってるつもりはないのだけど,不戦敗だった,ということ.
もう一つの理由はボリュームゾーンの埼玉県のイケてる県立高校が軒並み男子校なので,これまた「ガリ勉,理工系,男子校で経験不足」ということで,絶望的な状態となるのだった.
卒業したら,皆さん良い会社に入るので,そこからモテはじめるのですが... 本当,長年謎だった. という話を数日前に学部時代の友人たちにしたら,なるほど,っと理解いただいた次第.
本 What's New! には魂のことを書いているつもりなのですが,どうでもいい話で恐縮です.
7 月 6 日: ANA の "ビジネスきっぷ" は "ANAカード優待割引" になる
本 What's New! には魂のことを書いているつもりなのですが,実用的な話で恐縮です. 表題の通り,2026 年 5 月に ANA の国内線チケットの販売ルールが大きく変わるのですが, "ビジネスきっぷ" は "ANAカード優待割引" になる,ということだと理解したということです.
たとえば,2026 年 6 月 22 日に大阪-東京をエコノミー日帰りで往復することを考えると...
ANAカード優待割引 vs スタンダード 往復で買うと片道 16,095~16,355 10,705~13,000 変更手数料 無料 税抜運賃の約10% 出発時刻前取り消し 500 円 税抜運賃の約30% マイル 644 (100%) 515 (80%) プレミアムポイント 960 (280×1×2+400) 648 (280×0.8×2+200) (プラチナカードのダイヤ 2 年目以降で計算)
なので,PP 単価はスタンダードの方が良いのですが,変更手数料や取り消しのこと,さらには 1 回のフライトで PP そのものが 1.5 倍であることを考えると,これまで「ビジネスきっぷ」を利用してきたユーザーは「ANAカード優待割引」に乗るべきかなと思います.
また,片道だとANA カード優待割引は 16,920~17,180 となり,往復割が効いてます(スタンダードも同様ですが).2025 年 6 月の「ビジネスきっぷ」が往復で 33,880 とかなので, PP もマイルも維持しつつ,若干安くなった「改善」だと思います.こういう説明がネットに全然載ってないので,ビジネスユーザーの皆様のご参考と思いました.
JR 東海は,「リピーターを大事にしません」という宣言を2年くらい前にしたのですね(2023年8月に,12月をもってグリーンポイント廃止を宣言した). で,私は国内線で ANA の PP をためて海外出張の UPG に使う方針に変えたわけですが,じゃあ,JR 東海はどうなっているのか,っと思ったら,
なんと過去最高黒字!(新聞記事).
「23年秋に実施した、新幹線の「エクスプレス予約」の割引率変更も、増収につながった。」「外国人の利用が目立つグリーン車の稼働率が上がっている」ということだそうで.逃げて正解.
この丹羽社長というのは,我々の5歳上の旭丘-東大法で,周囲にいそうな経歴※なのですが(名前からして丹羽だし),まあ名古屋ドメスティック※※の完成形みたいなキャリアなので,関西のビジネスマンのマインドは理解できないんだろう.
この辺のディープ名古屋話は 2013 年 4 月 15 日: 多崎つくるへ.
6 月 25 日: What's New! 特別編:コナミ巡礼ダイエット
本ページでは,「一日一回一時間ほどコナミに寄って泳ぐ」ことを 一年間ほど続けることで,約 25 kg のダイエットに成功した経験について, その背景,方法,結果を記録しました. 日本全国のコナミスポーツクラブ(以下,コナミ) 40 数店舗を訪問しました. これはプールのあるコナミ 122 店舗の約 1/3 です. このイベントを「コナミ巡礼」と名付けました. 筆者は兵庫県在住の現役の大学教員なのですが,仕事をしながらでした. 海外出張時を除く,ほぼ全ての日に,毎日通いました. 2025 年 3 月は,海外出張がなかったので全ての日にコナミに行きましたが, その間,東京に 4 回,福岡に 1 回出張しています. 全国にコナミがあることは大変素晴らしいのです. コツは,「午前中を活用する」「出張先の旅程に組み込む」ことです. 元水泳部なので,メニューを組んでトレーニングしました. また,理工系の大学で研究室を構えていると,飲み会が怒濤のようにあります. これを一切妥協せず,サボらず,呑みながら通いました. その分,朝食と昼食を工夫しました. 53-54 歳時のことで,初老男性の皆様のご参考になればと思います.
長くなったので, What's New! 特別編:コナミ巡礼ダイエット
6 月 20 日: 検索エンジンのおすすめ duckduckgo
google のキモい情報規制に触れた.おかしいな,っと思ったら,
https://duckduckgo.com/ を知っておくべき.
僕の日記(当ページ https://washizu.org/og/ognew.html )には,検索窓がつけてあります.「あれ?あの記事っていつかいたんだっけ?」というのを知るために便利.たとえば「メタボの罠」って本を読んだのはいつだっけ?とか.
そしたら,何も出てこないのだな.セーフサーチとかつけてないのに.勝手に,僕の書いたことを「なかったこと」にしている.
これは「google 八分」→ google の検索結果に反映されないことによって,ネット上の「村八分」を実現する,ディープな人々の知ってるワード,状態になったのか?と思ったのですが,たとえば「博士 就職」みたいな,僕のウェブサイトでは定番の用語を入れるとちゃんと出てきます.
「ボッケリーニ」でも検索結果が表示されるので,鷲津研究室の中がOKで,日記がダメってわけでもなさそう.
つまり,僕がというより 「メタボの罠」って本 が,google 八分になってるようなのか.ってことで,自分のサイト限定をはずしてググると,普通に出てくる.なんなら,google books にも載ってる.禁書ではないのだ.
ということですが,なんだか google がキモいって気分になったし,実用上,自分の日記を検索できないのは「使えない」ので,google を捨てて DDG に乗り換えました.どうせ自分以外には使ったことある人いないでしょう.今でしたら,このページ右上の小窓にメタボって入力したら,DDG がどのページに書いてあるか教えてくれます.
6 月 14 日: 自分の経歴にちゃんと誇りを持て
ここ一週間くらい,若者たちと喋ってて思わず考えがまとまった話を書こうかなと.
結構多くの人において,自分の経歴に後ろ暗い部分がある人っていますやん.で,大人になってから,それをどう受け止めるか.いつまでも,恥だとか,否定的な感情で思っていてはいけません,という話.
ちょっとした不正をした子がいて,それを咎めたら,だって学部時代の友人は問題ないって感じで行動してたから,自分も問題ないと思いました,と.僕が,でもそれは悪いことなんじゃない?って言ったら,「しょせん○○大ですから!」って言う.いやいや,○○大のこと,僕はそういう風に思ってませんよ.そこ出身の立派な人もたくさん知ってますって言っても,通じない.ので,数日おいて,もう一回,いろんな人(とくに家族)と話して,反省するように言いました.
で,数日後,いろいろ考えてわかった,と言うので,了解しました.そのときに,冒頭の「自分の経歴にちゃんと誇りを持て」と言いました.
どうしてか.まずですね,これって,いわゆる社会的なランキングの中で,下の方から上の方まで,このことをグジグジ悩んでいたら,キリがないのです.「上」には上の悩みがある.僕の出身高校の1年下の子が,理3に受かる実績だったのに理1しか受けられずに自殺しました.「敗北者」とかいったメモを残したそうです.何年も受からず浪人してる僕からみたら,アホかと思った.まあでも,上の方は上の方で細かい.だから,この問題を引きずれば引きずるほど,人生の選択肢が狭くなって,そこに閉じ込められてしまいます.
もう一つの観点は,「不正をする」というのと隣り合わせだからダメです,ということ.自分の過去を隠したいって心理になってしまうと,ついでに,いろんなことを隠したくなる負のスパイラルに陥ります.この辺,上手に説明できないけど,直観的にそう思いませんか.自分の経歴という,自分が一番よく知っていることすら堂々と説明できない人が,自分が測定・設定・判断などしたことがらについて正しく説明できるとは思えないです.
うちの子は,皆さん産業人になるわけですが,不正をすることが一番悪いです.無能であることよりも,1万倍も悪いです.虚偽の報告をする,ミスを隠す,そういう事例がいっぱいある.でも,その一つ一つが,日本の工業製品に対する信頼をなくしていってる.誇りをもって,正しく作らないとダメなのです.
「ちゃんと習ったやろ?」って.その「習った」を,かなり,ちゃんとやってるのが日本の理工系の教育です.それに対して,誇りも持てないような人は,産業と関わってはいけない.ということなのだと思うのです.
PS:昔から僕のことを知ってる人は,ワシヅの癖に偉そうにって思うかもしれんけど(笑).オッサンの役割は,正論を言うことだと思います.若者は普通に正論を言うけど,オッサンになるに従って言わなくなる,言えなくなりますやん.
4 月 24 日: 我々はデータ小作人
テクノ封建制,ヤニス・バルファキス 著,斎藤幸平 解説,関 美和 翻訳,集英社(2025)を読んだ.
経済とかビジネスの本って,ほとんど読まないし, まして他人に推薦はほぼしないのですが,自動車会社に就職する直前に読んだ ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則, ジム・コリンズ、ジェリー・ポラス 著、山岡洋一 訳, 日経 BP(1995) 以来,他人に推薦できる本です.
GAFAM が封建領主だとすると,トヨタはテスラと一緒で封建陪臣の立場で,僕が「会社」としてイメージするのは,っとすると日本国民と異なり国民の休日のなくなったT公国民のシステムなのですが.
この公国は,まあまあ「うまくいってる」ように感じる.「自動車絶望工場」(by鎌田慧→もう知らん人もいるのでは)なのかと言われたら,結構そのイメージは違うように感じる.ラインに立ってないからなのかもしれませんが.
愛知県全体で,自動車共産主義みたいな状態になっている.もりころパーク(もうないけど)や春日井のウォータースライダーに相当するものを関西圏で楽しもうとすると,5倍くらい取られる.中学卒業するまで医療費は無料だった.何より住宅が関東や関西に比べて安い.有休消化率は,最後に見たデータではグループ企業で一番悪い J 社(笑)でも80%くらい.他はほぼ 100 %.健康診断ではCTスキャンが自動的についてくる.愛知県民あるいはT公国民は,どの程度この状況を客観視できてるか知りませんが.
さて,上記のバルファキスさんの描く「革命後」の社会なのですが.
僕は経済学を一度もちゃんと勉強していないのでアレですが,経済学ってマクロ経済とミクロ経済があるのでしょう.この人の議論って,全部を統合して議論しようとしてるので,自然科学者だったら「無理」って判断する話になってる.ミクロな系とマクロな系の支配方程式が違うから.その辺,どうなってるんだろう.
で,ミクロ経済しか多分想像できないので,以下は直観的に思うのですが.僕は掃除人や引っ越し屋といったエッセンシャルワーク(アンチ bull shit job) を20代で 10 年間経験してから,今はテックユニコーン企業(笑)の CTO もやってるので,なかなかのキャリアだと思うので,言えます.「基本給の部分を従業員全員で平等に分ける」ところまではアグリーです.が,ボーナスの分け方,というのが,絶望的にダメなんじゃないか?
「投票で決める」ということですが,たとえば今の大学院.大学院は,やっぱ学生を育てる機関であるのが第一なので,当然,学生の集客力が営業売り上げみたいなものに直結するわけです.ですが,ボーナスを「投票で決め」たら,多分,同僚に嫌われてる僕みたいな人は,どれだけ学生を集めても給料が上がることはないでしょう.
また,同僚の教員は投票に際して,まだなにがしかの判断ができるけど,掃除の人とか守衛さんとかは,判断できないのではないか.bull shit job の本で議論されてることとの整合性を取ることが絶対必要な気がする.
病院なら医師だの看護師だの臨床検査技師だの薬剤師だのが,軸受会社だったら軸受を設計開発する人が,レストランだったらシェフやソムリエが,といった感じで,その事業所で主となる何らかの専門職がそれぞれあるわけで,そこを横串で評価できるのかな,というのが一番違和感のあるところ.学歴を積む,専門性を高める努力をする,モチベーションをどこから担保するのかがわからなくなる.
もう一つは,この著者も技術革新の継続は必要だとは言ってるんですが,企業で新製品を開発するときに,コア技術を提示して社内で仲間を募集するって言ってます.技術者なら判ると思うけど,これでうまく行く技術って,3割くらいの分野?「スモールサイエンス」という言い方があるが,それが可能な領域.ハックして提案できる情報系の技術の多くはこれで大丈夫かもしれない.けど,「70人乗りのリージョナルジェット旅客機を開発します」とか,どうやってやるのかな.
T公国の中では,たとえば,技術革新の継続的な生成の方法については,結構頑張って構築してきた,と思うのですね.そのことと,現状の資本主義とはマッチした.愛知県では,余剰の資本を地方公共団体だの周辺にばらまくことによって,共産主義的なアイディアの良いところは既に取り込んでいる.やっぱ言われてるようにモノリシックな経済圏だから実現してるんだと思う.
っと,T公国万歳の「名古屋ドメ」的な視点から批判的にこの話を読んでいると(「日本はオワコン」ってバルファキスさんはモロに書いてるから,そこも楽しんで欲しい),じゃあ,テクノ農奴として位置づけられた我々に「革命」が到達して,どうメリットがあるのか,「うれしさ」を教えて欲しいということになる.
その際に,ちょっと心配気味に思い出すのが,チェ・ゲバラの日記.キューバ革命って本当に10人くらいで実現したんですよね.すごく興奮気味に書いてあるし,読んだ若い頃の僕はもっと興奮した.掃除夫とかしてたので.
ただ,俯瞰して歴史的にみたら,共産主義革命の中では,ポルポト,スターリン,毛沢東とかと並べてカストロを考えたら,どうも,それほど悪い革命ではないように思う.音楽とか聴いてたら,ショスタコの交響曲と「ブエナビスタソーシャル...」との違いがあるくらい.でも,当時の「大人」たちは,随分と困ったんじゃないかなあ.
ここを突っ込まれるのが心配なので,著者はものすごく慎重に,左翼というものの本質は違うんだ,と本書の前半を通して語っているのですが,ちょっとまだ,若い頃にできた傷のかさぶたが取れてない感じがする.あくまでも感じですが.
4 月 21 日: 転職とか昇進(独立)の挨拶
は,必要だと思います.
なんか知らんけど,そういうことをしない人が年々増えています. なんだろう.栄転を威張ってるみたいで,世の中に対してそっとして おこうという気遣いか何かなのかしらん. 人事が確定するまでは,公表しないのは常識です. 事前に連絡・相談すべき人を厳選するのも常識です. が,実際に転職とか独立とかした後だったら, 連絡したらどうかと思うのです.
こういう情報をキャッチすることにあざとい人と,そうでない人がいます. わしは,チャキチャキしているように見えて,そういうことに鈍感です. たとえば,共同研究している東京の大手私大の教授が, 某北の方の旧帝大に移られた,のを知りませんでした(笑). 学生が教えてくれた.これから論文を出すというのに...
わしが思うに.プラクティカルに,連絡先を教えてくれないと 困るじゃん,というのがあります. 上の件でも,たまたま連絡をとろうと思わなかったので大丈夫でしたが.
あと,最近は,「本当に偉い人」という自覚を持ってる人が 大変少なくなっているのではないかと思います. 要は,このポストに就いたら学術界をリードするのは自分だ,という自覚. いえ,ちゃんとしたポストなんだったら,そういう自覚をちょっとは 持っていただかないとって思うのです.
あとは,単純に目出度いことなので,別ルートで聞くのは不愉快です. まあ,自分ごときに連絡してこないのは当然だわな,って関係だったらともかく, 最近は,学生時代からその人のことを知ってるよって関係も結構あるわけです. だったら,こちらは単純にお祝いしたいじゃん.それをさせないって, なんだかなあと.
自分でも,9年前に転職したときは 300 件くらいメールを出しました. まあ,葉書を出すような時代でもないしな,っと. そしたら,大体の方々は,今までお疲れさん,良かったね, 頑張ってね,っ的なお言葉をくださいました.
ビックリするようなコメントは 2 件だけでした. 1 件は,会社の人事の方で「未提出の書類があるので出すように」とだけ 書かれていた件. 2 件目は,「あの駅前に神戸大があるのは知ってるが,兵庫県大なるものが あるのは知りません」っていうお言葉.いや,そう思ったとしても, 普通は書かないと思うのですが(笑).
逆にいうと,メールを出しても 1 % 未満しか,ギョっとする返事は来ませんので, 普通に出したら良いじゃんって思う次第.
4 月 19 日: X をやらない理由
最近,博士院生が X でこんな話題があるって話をしていました. JST の博士用のプログラムのイベントに出なかったらプログラムを 首になったどころか大学自体がクビになったとか何とか. まあ僕も院生の頃は孤独だったので,そういうネットを良く見ていました.
けど,あれって見ててもあまり意味がない.(アカデミアっぽい)世の中に対して文句を言ってる人って,圧倒的に文系・生物系・物理系が多くて,(アカデミア的な意味で)リア充なトライボロジストみたいな人はほとんど発言していないから,毒される.理学系の文化を浴び続けて,企業研究所に入ったら全く別世界で(もちろん企業研究所はアカデミアともちょっと違うけど),拍子抜けしたのを思い出す.親戚は医者ばかりなので,またそれは別世界だと感じる.普通は,そっちとこっちを出たり入ったりしないので,バイアスのかかったまま一生を終える.でもそれって,世の中をすべて理解したいという学問の基本的な姿勢からすると極めて問題な筈なのだけど.
で,久しぶりにいろいろ眺めてたら,今の話題はハーバード大学から政府が3000なん百億円の資金を引き揚げるって.ポリコレ的な問題で.そうなんですか... これも,科研費全体で2000何百億円と比較してぶっ飛んでるって話を書いてる人がいて,確かになと思ったんですが(ちなみに世界上位の企業の研究費は一社で1兆円超えてますが).
まあでも,落ち着いて考えると,自分にとっては,どうでもいい話題かも.誰かが,阪大とハーバードが合体したら東大に勝てるって話をしてましたが,それを実現するタイミングかもしれませんが(笑)
本業(化学なら化学の研究)をちゃんとやってるよと.余った時間を何に使うか,というときに,ハーバード大学がどうって「大変有名な話題」にシンクロすることよりも,たとえば,昨日の夜は息子とコンスタンチノープルの陥落について語り合ってたのですが,もっと,そういう自分の頭にとって大事な話をした方が,自分らしさを成就できる気がするのです.
マスコミ的な仕事(僕が半年弱やってた理工系出版社とか)に生きてたらそれも大事で,たとえばサイエンスライターさんとかのXを見てると,確かに面白いですが.でも,僕の場合は,自分の魂のオリジナリティの方が大事だなと,しみじみ思った次第.炎上するのが怖いとかもありますが,今回は,もっとしみじみとそう思った次第.
あと,学振と JST SPRING の違いですが,Xを見ると外国人が4割とってて,その大半が中国人ってことが問題になってるようでした.まあでもこれって,日本人が博士課程にあがらないこと自体が問題としか言いようがないような.
もっと大事な学振とJSTの違いを言います.学振は,まあ科研費の審査みたいに全国の先生方にも回ってくる,全体的な話です.JST は大学に個別に来ます.どうなるかというと,JST の方は東大京大に不利になります.学振は,ぶっちゃけ「いけてる先生の子分のいけてるテーマ」が当選しがちになります.だから,東大京大のいけてる研究室に所属してたら当選確率がドンと上がる.
院生の頃の僕は,一応東大でしたがイケてない研究室だったので,学振なんて,まず当たらない.一方,高専の助手のポストなど,地方人が有利なシステムが当時からもあった.ので,地方人のことも,あいつら良いよなあ,都で勉強してないのにアカポスに就けてって,正直うらやましかった.
ということで,今の僕の立場としては,地方人のボスの側になったということで,JST はありがたいと思うわけです.真面目に言うと,「いけてる先生の子分のいけてるテーマ」は,確かにアカデミアの中だけで見たらキラキラしていて大事ですが,もうちょっと広げて考えると,キラキラばかり見てる人たちには見えない視点もあります.僕がここ10年苦労している「流体とブラウン運動の連成」なんて,企業人なら一瞬でわかってくれるけど大学人にはサッパリなテーマです.そういうことを,地方のイケてない研究室ではやってるわけで,そこにも,ある程度の,主要ではないけど博士院生が食える程度のお金が来ても,長期的に見たらバチが当たらないと思いますよ.そういうことです.
僕自身は,研究室を立ち上げてからは,そういう地方人の苦労をしたくなかったから(爆),基本的には「企業の下請け」をずっとしてきました.だって,企業が1000万くれたら,東南アジアの東大生みたいな人をポスドクとして雇って,世界的に見たら日本の中央なんてどうでもいい研究展開をできますので.基本はそこで,今の職場の院生が聞いてるよりはるかに優秀だったのはサプライズ.で,物理や化学の学会の偉い先生が何を考えてるかなんて,どうでも良いって暮らしを続けられました.これは企業研究所にいたときと変わらないスタンス.
でも,そうこうしているうちに,中央の先生とも,次々とお友達になってしまって,そうすると,ああ,あっこは学振をガンガン取ってるなあって,東大の中にいたときの昔の感情みたいなものを思い出してしまって,頭の整理をしなきゃいけなくなった→イマココ.
4 月 6 日: 大学ベンチャー周辺の鼻息の荒さ
「 コオロギ食、コンビニ全国展開目前で挫折 無印良品で話題も陰謀論で炎上」 という記事で,
>私は、日本で大学発のスタートアップが増えない現状に課題を感じています。大学の研究者は論文の数で評価され、スタートアップを経営しても評価は変わりません。このため起業する研究者はなかなか増えません。
というご意見がありました. でも,大学ベンチャーを作ることは,研究教育業績じゃないんだから,大学からの高い評価なんて要らないと思います.スタッフや大学院生に給料を払うことが可能になり,自分もボーナス1回~数回分,増えてくんだから,それで良いじゃないと思います. 2024 年 8 月 31 日: 実務家教員 で述べたように, アカデミアの評価はあくまでも学問で行うべきです. そうしないと,お金を引っ張ってきたから何ちゃらラボのボスに据える,みたいな スキャンダルになりかねません.
この方は若手だから,そういう風に思うのかもしれませんが.
オッサン的には,大学から褒めてもらいたいと思うのは,我々が「上納金」を毎年キッチリ納めていること.他人からお金をもらったら,ありがとうと言って欲しいです(笑).どなたも仰いません.利益をあげてるのは当社だけだそうですが.
で,思ったのですが.大学ベンチャーのイメージとか,関係人物の皆さんの,鼻息が荒すぎるんですよ.
これって,「乳を搾る」ようなものだと思います.本来だったら,子牛が産まれたら自然に乳は出てくるもので,自然に任せたら良いのです.が,どっかに一頭,巨大乳の牛がいたからか知らんけど,凄い勢いで搾ろうとする人々が現れた.母牛の方でも,あいつみたいに凄い勢いで乳を出すぞって人が現れた.
本来だったら,金なんて借りなくて起業できる程度で良いのです.SOHO って忘れたの?皆さんが,ちょっとずつ,出来る範囲で,技術の社会実装を行っていけば,その中から驚くようなイノベーションが生まれてくるかもしれないという程度のこと.当社みたいにビジネスとして最初の瞬間から成り立っていたら,それで世間の役に立ててるんだから,それで良いではないか.何故,そう考えない?
VC の方はそれはそれで,一銭も利益を生み出してない会社にばかり投資しようとするし.詐欺師の馬鹿しあいみたな状況をなんとかして欲しいです.これには理由があって,日本の分子生物学が恐ろしいほどの権威主義 (アカデミックですらない. 日本分子生物学会の理事名簿を見たらわかります) なので,実際に役に立ちそうな大学ベンチャーを支援せずに, 旧帝大のいかにもな人にしか投資しないからです. この方法だと,ただただ税金を溶かすだけです. 生物学以外の理工系では,そんな可笑しい状況ではないのですが, 大学ベンチャーの多くが生物系です.
ということで,そういう人々とは関わらずに,心穏やかに生きていけば良いではないかと. 昨今は,大学が起業の邪魔をしないようにはなりつつある.また,ちょっとした手助けが動き始めている.それで良いではないか.
この人は「敗軍」になったけど,僕は負けてない.本日述べたような論はどこにもなくて,負けてない人に話を聞きに来る人も誰もいない.
3 月 20 日: コンプリートすること
スポクラの守口店に行きました.ここは建物が全体的にオシャレ.安藤忠雄系.丸太町店も建物がかっこいいけど,方向性が異なる.プールも2階まで吹き抜けてる上に三角屋根.
どこに行っても,よほど混んでない限りメニューは大して変わらないのですが(50m ずつに切ってるから,混み具合によってロバストにこっちが内容を変化させてる),新しいところに来たら,最後のダウンで,背面でブレストのキックで,要はあおむけの蛙状態で天井を眺めるのを趣味にしています.ここは,全国指折りの良い感じ.ちなみに,ポートアイランドスポーツセンターの50mプールも良い感じ.川重カラーの黄緑になってる(笑).ここは三角屋根の中央から空が見える.
兵庫県は,かなり頑張って,残るのはジェームス山,川西,三田の3店.京都は意外にコンプリートしてて(少ないから),あとは伏見と八幡.大阪は,都心部はほぼ制覇したんですが,郊外は行ったのが岸和田東くらいか.今日は定番の西北が定休日で,三宮に行くのも何だし,守口は家から近くてキッズとも被らないので行きました.
いえ,先日の九州出張には博士院生の一人といったんですが,福岡県は2店舗で半分行ったので,あとは大野城と北九州だといったら,「僕ならコンプリートを目指します」という.私の思想を,わかってない.コンプリートが優先なんじゃないんだ.あくまで,普通に生活してて,たまたま制覇した,という状態が好きなんだ.
よくマイルをためるために修行するという方がいて,その Youtube とかを見るのも好きですが,自分では絶対にやりません.やっぱ人生の目的は「知の巨人 笑」になることであって,その道すがら,たまたまたスポクラをコンプリートしちゃったとか,ステータスがダイヤになったとか,そう言いたい.
こういうこと考えるとき,北村透谷とか石川啄木の人生について考えるのです.25歳とかで死んでるけど,圧倒的な存在感がありますやん.絶対,彼らは何かをコンプリートしたことなんてない.世の中の全部を見てない.見てないけど,本質をつかまえて,それを表現して,決定的な役割を果たした.
3 月 17 日: 起業する際に
お蔭様で,立ち上げた会社は初年度から 3 期連続黒字です. で,本当に小さい事業ですが,会社経営についてつらつら考えることがあります. まず,大学教員でベンチャーを作ってる人って大変少ないので, 相談相手がいません.大学の研究室の運営について,だったら皆さんと 普段の会話がありますが,ベンチャーはちょっと違うので,特有の悩みを 相談できません. 2024 年 12 月 30 日: 御礼 の中ほど書いたように,うちの会社には「福利厚生」があります. 素晴らしいことなのですが,偶然ネットで見つけました.誰にも相談せず,自分で決断して, 事務の人にお願いしてサービス開始しました. 実は,事務の人,というより経営の片腕様なので,この方=社員には相談しているのですが.
ところで,起業家の女性がセクハラにあう,という記事を Yahoo! ニュースで見たのですが, コメント欄に,「エンゼル投資家」などというものと関わるのがいけない,などなど, いろいろなことが書いてあって,参考になると思いました.
僕も自分のお金100%で起業しましたよ.普通はそうすべき.セクハラは論外だけど,「起業業界」なんかと関わるのがいけない.誰にも相談できない,のが正しいと改めて思った.
起業系のイベントというのがあって,僕もたまに誘われるのですが,一度も出たことがありません.ああいうのに「出させてもらう」というのが,既にカモられる第一歩というか,ネタにされる第一歩というか.何のネタかというと,なんの役にも立たないイベント業というのが世の中には結構あって,そのネタになるということ.自分のビジネスの実体とはリンクしない.
普段,将来の顧客の皆様と出会う主たるイベントである「学会」は出ますけど,それ以外の,商工会議所のイベントとか,高専の技術センターのイベントとか,メーカー内部のセミナーとか,O さんが誘ってくれた技術士の会とか,T さんが誘ってくれた考古学者の会とか,そういうアウェイっぽい会くらいには出ます.
でも,そういう会って,必ず「呼ばれて出る」状態で参加します.「呼ばれて出る」のと「出させてもらう」のは,だいぶ違います.「大学見本市」がそのボーダーくらいで,オンラインの奴に頼まれて出させてもらった,けど全く何の意味もなかった.オンサイトのときは良いという話も聞きますが.
こういうことを最初何で学んだんだろうと思いだすに,20代前半,チェロとアコーディオンのユニットをやってるときに,ストリート系音楽のイベントに,半分サクラみたいな形で出させてもらった,ときです.コンテストみたいな形式になってて,本気で「出させてもらってる」という参加者もいるわけです.あー,こういうのは二度と出てはいかんな,っと思いました.普通にストリートで演奏する方が楽しいし,金になるかどうかは場合によるが,正しい.音楽をやるって,すごく人生の勉強になる.
起業系イベントで,コンテストみたいな形式のがありますやん.ああいうのって,意味があるのでしょうか.申し訳ないが本気でわかりません.
3 月 2 日: イギリス兵のように生きてきた
ここ数か月で,生活の上で大きく変わったことは, 2024 年 12 月 30 日: 御礼 や 2024 年 10 月 16 日: ひたすらロング に書いたように,毎日水泳をするようになったこと. 1 年と数か月で変わったことは, 2023 年 9 月 5 日: さらば新幹線 に書いたように, 移動手段として新幹線を捨てて飛行機に変わったことです.
そちらの記事には書かなかったのですが, 毎日水泳をする,というのは大変リスキーなことです. 何にとってリスキーなのか,というと,一言でいうと「出世」です.
前職の研究所にいるときは,近所に口論義公園という素晴らしい室内 50 m プールがあって, 毎日,泳ぎに行こうと思えば行けました.裁量労働制になったら,余計に状況としては 良かったのですが,行ってませんでした.そのときは,職場にパートさんとか派遣社員さんとか, 非正規の方が沢山おられたので,正社員があまり怠けていると示しがつかない. 僕は 20 代の頃はずっと自分自身が非正規のフリーターだったので, 正社員が怠けるとやる気がなくなるのを肌感覚として理解していました. 口論義公園には毎日は行かなかったのですが, 前職で単身赴任の週末婚をしていた最初の 5 年弱の間は, 仕事が終わった後は藤が丘のスポクラで月曜から木曜まで,毎日夜に泳いでました. 週末は東京の家で過ごして,月曜日に朝イチの新幹線で名古屋にいって, 金曜日に東京に帰る,という間の日の夜は単身で暇なので,泳いでました.
大学に移ってからは,仕事が終わった後にポートアイランドの神戸市スポーツセンターで 泳ぐことが,週に 0~2 回くらいありました.公営のプールは午後からしか やっていないのと,夕食を作る担当なので,早めに仕事を切り上げられる夕方しか 泳げなかったから,必然的に週に 0~2 回になっていたわけです. ちなみに,水泳では痩せません,というのは,週に 0~2 回程度しか 泳がない場合のことです.毎日泳いでいたら痩せます. というか,お腹の脂肪が取れた上で肩が張った,水泳部体型になります.
つまり,現役の労働者が毎日泳ぐ,ということは,午前も泳ぐ,あるいは,出張先でも泳ぐ,ということです. かなり,泳ぐ時間を能動的に捻出する,ということです. 一回の時間は,2km ほどで 45 分くらい.着替えやシャワーを入れても 1 時間ちょい. 仕事場まで行く乗り換え駅で行くので,その意味でも, 大した時間のロスではないのですが,まあまあです.
ちなみに,今の職場の部屋には秘書さんがおられるのですが, 大学業界はブラックなので⇒土日に仕事が入ることもザラだし,自宅でかなり作業しているし, ということで,以前の正社員と非正規が云々という話は,免除していただくことにしました.
単身赴任時の夜間に泳ぐことや,週に 0~2 回泳ぐことは,まだ何というか 「健康維持」の範囲でした.他に運動とかしませんし. でも,毎日泳ぐことは,明らかに「贅沢」です.
もう一つ,贅沢をしています.それは,出張の行き帰りに伊丹空港を通る際に, 時間があったら, 大阪エアポートワイナリー に寄ることです.ラウンジにも寄るのですが,ラウンジは仕事ができる場所です. 論文の査読レポートを書くくらいの作業ができます. ワイナリーは,一人でワインを呑みます. これは,自分にとっては画期的な贅沢です. すごく悩みました.プライオリティパスのレストラン特典が 楽天プレミアムカードからなくなって, さらに,ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズ プレミアムカードという 年会費 8.8 万のカードに切り替えてもレストラン特典がなくなって, さらに別のカードにしてまで,この贅沢を追求しています.
そのとき,ふと思ったのです. これまでは,イギリス兵のように生きてきたな,と. 19 世紀に世界を支配したのは大英帝国です.パックス・ブリタニカ. その原動力となったのは,俗説かもしれませんが, イギリス兵はまずい飯でも戦うけど,フランス兵は食事が大事,という話です. フランスがロシア侵略で失敗したのは,飯を調達できなかったからだ,という話. 一方で,イギリス兵はオーストラリアやカナダやさておき, インドやアフリカの奥地でも働いている.正しいかどうかとかは知りませんが.
確かに,これまで一人でいるときに,フランス料理はおろか, 飲み屋で一人呑みすることすら,ほぼ,ありませんでした. 牛丼とかラーメンとか,そんなんばっか. (参考 2000 年 2月25日: 鰯でいいやんか 若い頃に既に書いてる.「どっちみち, 驚くような発見は自分で しなければならないのです. 驚くような人や物事と出会ったとしても, そのことに驚くのは自分の感性なんですから. 」). 二人以上のときは別ですよ.美味しい店を探してはいることは多いです. これは,一人と二人以上だと,全く食べる意味が違うからです.
「自分へのご褒美」という概念がなかった. それはすなわち,オンとオフという概念がない,ということです. あらゆる局面において,知の消費者になることを恐れて, 知の生産者たろうとしていた. そして,なんだかんだ言って「知の巨人(笑)」になりたかったのだと思いました (参考 2021 年 6 月 23: ニューエイジ時代の「知の巨人」立花隆氏.RIP). 科学者として通常の仕事をする以上に,作曲をして,詩を書いて,評論をして,という感じです. 作曲家としてはアイヴスやボロディンのように生きたいし, 詩人が他の職業を表面上持っているのは通常のことです.
もうちょっと俗な言い方をすると,「出世を諦めていない」という言い方だったら 伝わりやすいかも.だって,毎日プールに行ってたせいで, あるいはワインを呑みすぎたせいで, 研究員から主任研究員に,あるいは准教授から教授にあがれなかったとか, 思ってしまうのは嫌じゃないですか. 他人とワインを呑むのは,視野を広げるという意味で,意味がありますが, 一人で呑むのは,単なる贅沢です.酒が好きなら家で安い缶チューハイを呑めば宜しい.
ということで,判りやすい言い方でいうと,定年まであと 11 年ですが, まあ,K 大や H 大から呼ばれたり,学術界の偉い役職に就いてくれと言われたら, 別にやりますが,積極的にイギリス兵のように生きるのは,そろそろやめようかな,っと 思ったわけです. そんなことよりメタフィジカルに言うと, 余裕を持って,まだ曲が書けたら,詩が書けたら,書こうかなと思っている次第.
この年になるまで「緊張」していた,ということかと思います. 研究者の人には多いと思います.別に,そういう緊張をしていなくても, 良い業績を出す人は多分沢山います.なので,自分が必死だ,ってだけなのだと 思うのですが,これはちょっと記録するに値するかなと思った次第です. やっぱ,怠けてて知的生産ができるわけないじゃないですかと. 若い人が読んでるみたいなので(笑),それくらい緊張感を持って生きろよ, って偉そうに言いたいということです.
1 月 26 日: 神戸と兵庫県
今年も宜しくお願い申し上げます.
ところで,兵庫県民の自己評価,というのも,ここ数年の僕の研究テーマです.
実態以上に外部評価が低い名古屋にかかわってきたせいか,実態以上に外部評価の高い神戸について,老婆のような心でじっとり眺めています.でも,神戸人って自己評価が思ったより高くない.
関東人に対しては,神奈川県との比較をすると,とても分かりやすい.神戸って広大な神奈川県が半径20kmくらいにギュっと詰まってる素敵で便利な街なのです.山下公園や中華街,みなとみらいに相当するものが三宮周辺に全部ある.横浜からみたらはるかに遠い箱根の温泉が,裏山の有馬温泉としてある.同じく遠い丹沢が裏山の六甲山.材木座や稲村ケ崎に相当する海岸が,市内の須磨にある.100kmも先の伊豆半島に相当する淡路島が,市内から出てる橋の向こう側にある.「伊東に行くならハトヤ」と「ホテルニュー淡路」の歌がそっくりでしょう.
こういう説明をしたら,すごくコンパクトに名所がまとまってると理解できるはずなのですが,こういう説明を見たことがない.
兵庫県全体に広げても一緒で,兵庫県は
1. 和牛の起源(六甲山の水が良質だったので,神戸港に外国船が沢山来た.欧米人が牛を要求したのが黒毛和牛の97%を占める但馬牛ブランドのはじまり.)
2. 日本酒の起源(播磨風土記に日本酒誕生の記載あり.1600年代に伊丹の鴻池が清酒の製造法を考案,灘と伏見の酒が国内を席捲.1920年代に兵庫県農業試験場で日本酒米の6割を占める山田錦を発明.)
3. 日本の起源(720年代に書かれた古事記・日本書紀に記載あり.)
4. 世界遺産・姫路城
なので,「肉と酒(魚もうまい)」があれば,観光には十分ではないかと思うのです.が,こうやって正面から兵庫県は日本一だという言い方をする人に出会ったことがない.まあ,自他ともに肯定感の最強っぽい京都人が身近にいるのがいけないのだろうか.